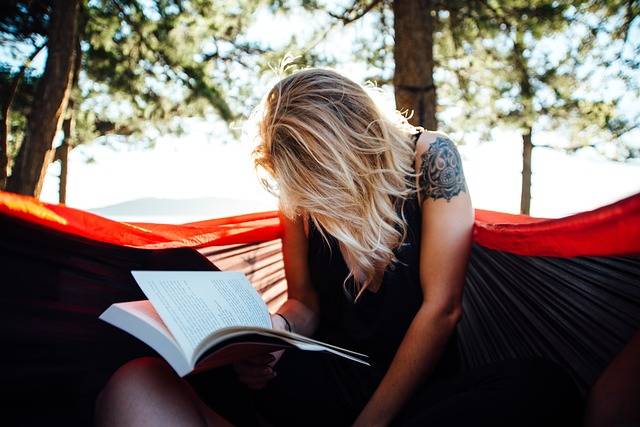目次
- 共感性羞恥とは
- 他人の失敗をあたかも自分の失敗のように感じる
- 共感性羞恥の他の呼び方
- 決して病気ではない
- 発達障害と共感性羞恥には関係がある?
- 現段階では関係性は認められていない
- 共感性羞恥の特徴
- 現実でも物語でも他人に強く感情移入してしまう
- 恥ずかしい場面を見ていられず逃げてしまう
- お笑い番組などで芸人がスベっているとチャンネル変更
- 他人が笑っているところで笑えない
- 共感性羞恥になってしまう原因
- 他人を自分に脳内で置き換える
- 共感性が特に強い
- 恥ずかしいことになるのが怖い
- 共感性羞恥にならないためには
- 物語を見るとき自分と他人を割り切って考える
- もともとは心理学の世界からの言葉
- 共感性羞恥は心理学の世界からきた言葉
- 共感性羞恥の症状チェック
- 困難を乗り越えるドキュメンタリーが見ていられない
- ドッキリをかけられている人を見ていられない
- 他人がかわいそうな場面を見ていられない
- 笑うシーンなのに恥ずかしくなり見ていられない
- 他人の失敗などSNSの投稿を見ていられない
- 共感性羞恥の治し方
- 治し方は対策と同じで、「割り切って考える」
- 少しずつ慣れていくことが大事
- 他のことに注意をそらす
- 共感性羞恥の人には自覚症状がある?
- 周りの人もその感情を持っていると思っている
- そもそも共感性羞恥という症状を知らない
- 言葉を知らないだけで自覚はある
- 共感性羞恥でも形は様々
- 苦しいのは見れるけど恥ずかしいものは見れない人も
- コメディは大丈夫だけど、スベっているのはちょっと
- 共感性羞恥はいろいろ
- 共感性羞恥は悪いことではない!
共感性羞恥とは
via pixabay.com
「共感性羞恥」とは自分が恥ずかしいと思う行動や失敗を他人が行っているのを見たときに、まるで自分が体験しているかのように自分も恥ずかしさを感じてしまう感覚、感情のことをいいます。
耳慣れない言葉ですが、実は経験したことのある人は少なくありません。では共感性羞恥とはどのようなものなのか、詳しく解説していきます。
耳慣れない言葉ですが、実は経験したことのある人は少なくありません。では共感性羞恥とはどのようなものなのか、詳しく解説していきます。
他人の失敗をあたかも自分の失敗のように感じる
via pixabay.com
ドラマや映画の中で登場人物がこれから失敗するかもしれない・・・となんとなく感じたとき、それ以上そのシーンを見ていられなくなることはありませんか?そして実際にその人物が失敗してしまったら、予測していたにもかかわらず非常に動揺してしまうのです。
本来他人が失敗したりミスを犯してしまったとしても、見ている自分には全く関係のないことです。そのことはわかっているはずなのに、まるで自分が失敗してしまったかのように感じてしまうのです。
また、失敗するかも、と予測した時点で「失敗したくない!」とその状況を回避しようともします。このように、他人の失敗に対して心が動揺し、自分のことのように感じてしまう心理状態が共感性羞恥と呼ばれるものです。
本来他人が失敗したりミスを犯してしまったとしても、見ている自分には全く関係のないことです。そのことはわかっているはずなのに、まるで自分が失敗してしまったかのように感じてしまうのです。
また、失敗するかも、と予測した時点で「失敗したくない!」とその状況を回避しようともします。このように、他人の失敗に対して心が動揺し、自分のことのように感じてしまう心理状態が共感性羞恥と呼ばれるものです。
共感性羞恥の他の呼び方
via pixabay.com
「共感性羞恥」は、1987年にMillerが定義した英語の「empathic embarrassment」を日本語訳した心理用語で、「きょうかんせいしゅうち」と読みます。「empathic embarrassment」は「共感的羞恥」と訳されることもあります。
また「観察者羞恥(かんさつしゃしゅうち)」と訳されることもあります。ただし、厳密には、「共感的羞恥」と「観察者羞恥」は同一の意味ではなく、「観察者羞恥」は桑村幸恵氏が「共感的羞恥」と区別してつけたものです。
また「観察者羞恥(かんさつしゃしゅうち)」と訳されることもあります。ただし、厳密には、「共感的羞恥」と「観察者羞恥」は同一の意味ではなく、「観察者羞恥」は桑村幸恵氏が「共感的羞恥」と区別してつけたものです。
決して病気ではない
via pixabay.com
共感性羞恥とは、その心理状態を表す言葉であり、障害や病気の名前ではありません。心理用語は「現象」や「効果」「理論」を表す場合が多く、「共感性羞恥」もそのような心の状態を表す言葉になります。
また、この現象(このような心理になる状態)自体も病的な症状ではなく、日本人の10%の人が当てはまると言われています。10人に一人は経験があるということは、比較的よく起こること、と言えるでしょう。
本人がこの症状を自覚している場合が10%と考えると、実際にはもっと多くの人が経験していると言っても過言ではありません。
また、この現象(このような心理になる状態)自体も病的な症状ではなく、日本人の10%の人が当てはまると言われています。10人に一人は経験があるということは、比較的よく起こること、と言えるでしょう。
本人がこの症状を自覚している場合が10%と考えると、実際にはもっと多くの人が経験していると言っても過言ではありません。
 嫌なことを忘れる方法!恋愛や仕事の嫌なことを忘れる脳科学的な方法 - POUCHS
嫌なことを忘れる方法!恋愛や仕事の嫌なことを忘れる脳科学的な方法 - POUCHS「嫌な出来事を忘れたいけれどなかなか頭から離れない」、「嫌なことがいつまでも忘れられない」と悩んでいる方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。恋愛や仕事などで忘れたいほど嫌なことってありますよね。ここでは、嫌なことを忘れる脳科学的な方法も一緒にご紹介します!
発達障害と共感性羞恥には関係がある?
via pixabay.com
発達障害のうち「アスペルガー症候群」は「共感性」というキーワードと密な関係がありますが、アスペルガー症候群は共感性が低いことが特徴です。
「共感性羞恥」の場合は逆に共感性が高い人に見られることが多いため、関係性があるとは言えないでしょう。合わせて「学習障害」「ADHD」においても、共感性に焦点をおいて考えてみます。
「共感性羞恥」の場合は逆に共感性が高い人に見られることが多いため、関係性があるとは言えないでしょう。合わせて「学習障害」「ADHD」においても、共感性に焦点をおいて考えてみます。
現段階では関係性は認められていない
via pixabay.com
発達障害は他人と異なる特徴的な言動が見受けられることもあり、「共感性羞恥」もその特徴の一つなのではと考える人もいるようですが、結論として関係性は認められていません。
発達障害の中でも「ADHD」のタイプは共感性が強い傾向にあり、共感性羞恥と関係があるように見えますが、それがADHDタイプの人すべてに当てはまる特徴とは言えません。「アスペルガー症候群」「学習障害」でも共感性羞恥の人は存在しています。
これらの割合は健常の人と比較することができず、発達障害とは関係なく「個人の性格的要因=個性」に起因するという見解が有効です。これまでも発達障害との関係の研究は進められていますが、現状では、優位な相関関係はありません。
発達障害の中でも「ADHD」のタイプは共感性が強い傾向にあり、共感性羞恥と関係があるように見えますが、それがADHDタイプの人すべてに当てはまる特徴とは言えません。「アスペルガー症候群」「学習障害」でも共感性羞恥の人は存在しています。
これらの割合は健常の人と比較することができず、発達障害とは関係なく「個人の性格的要因=個性」に起因するという見解が有効です。これまでも発達障害との関係の研究は進められていますが、現状では、優位な相関関係はありません。
共感性羞恥の特徴
via pixabay.com
では実際にどのような状態が共感性羞恥と呼ばれる状態なのでしょうか。その代表的な特徴を紹介します。
現実でも物語でも他人に強く感情移入してしまう
via pixabay.com
共感性羞恥の状態は、テレビのドキュメンタリーであれドラマなどの作り物語りであれ、とにかく自分ではない他人に強く同調し、共感している状態です。ただし、小説を読むときにあえて物語に入り込むこととは違い、相手への感情移入はほぼ無意識に行われているといえます。
そもそも羞恥心とは、恥と感じる言動をしたことによって生まれる感情で、自我や自尊心の延長にある概念です。つまり「自(みずから)」の行いから、自らが感じる感情なのですが、他人の言動を見ても同様に羞恥を感じるということは、それだけその相手に気持ちが入り込んでしまっているということです。
共感性羞恥を感じやすい人の特徴として、羞恥だけではなく、あらゆる面で相手への共感や感情移入は強いといえるでしょう。
そもそも羞恥心とは、恥と感じる言動をしたことによって生まれる感情で、自我や自尊心の延長にある概念です。つまり「自(みずから)」の行いから、自らが感じる感情なのですが、他人の言動を見ても同様に羞恥を感じるということは、それだけその相手に気持ちが入り込んでしまっているということです。
共感性羞恥を感じやすい人の特徴として、羞恥だけではなく、あらゆる面で相手への共感や感情移入は強いといえるでしょう。
恥ずかしい場面を見ていられず逃げてしまう
via pixabay.com
目の前で誰かが失敗していたり、それによって周りから笑われている状況に遭遇した際、まるで自分が笑いの的になっているような気がしてその場から逃げてしまうことがあります。
また、今まさに起こっている状況だけでなく、もしかしたら起こるかもしれない、恐らく起こるであろうと、恥ずかしい場面が起こることを察知、推測した時点で、その瞬間を見届けることができず立ち去ったり顔を背けたりするでしょう。時には同行している友人などにも見せないように気をそらさせたりすることもあります。
また、今まさに起こっている状況だけでなく、もしかしたら起こるかもしれない、恐らく起こるであろうと、恥ずかしい場面が起こることを察知、推測した時点で、その瞬間を見届けることができず立ち去ったり顔を背けたりするでしょう。時には同行している友人などにも見せないように気をそらさせたりすることもあります。
お笑い番組などで芸人がスベっているとチャンネル変更
via pixabay.com
1 / 4