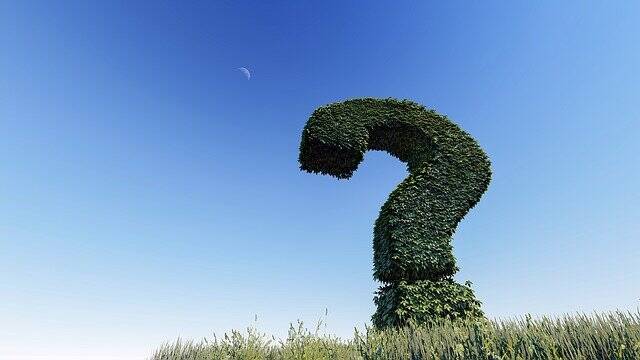目次
簡単な字なのに読めない!「予す」ってどうやって読むの?
via pixabay.com
「予定」の「予」に、ひらがなの「す」。どちらも簡単な文字ですので、小学生であっても読み方が分かりそうなものです。しかしながら、その二つが組み合わさって「予す」という単語になると、途端に読み方が分からなくなる人も多いでしょう。
熟語であれば単語の意味からなんとなく想像することもできますが、「予定」という意味の「〇〇す」という言葉が思いつかず、イメージができない人も多いのではないでしょうか。そこで、「予す」という言葉について解説していきます。
熟語であれば単語の意味からなんとなく想像することもできますが、「予定」という意味の「〇〇す」という言葉が思いつかず、イメージができない人も多いのではないでしょうか。そこで、「予す」という言葉について解説していきます。
「予す」の読み方は?
via pixabay.com
多くの人が読めない「予す」という単語。「予定」や「予知」という使い方をされる「予」という感じですので、「想像す」や「イメージす」のように、無理やり読み方を考えてみるという人も多いのではないでしょうか。
読めない漢字や単語がある時、感じの持つもともとの意味から連想するのは正しい方法です。しかしながら、「予す」の場合はそのような連想からでは正しい読み方を導き出すことは難しいでしょう。
実は「予す」は「ゆるす」と読みます。これはなかなか知らないという人も多いのではないでしょうか。
読めない漢字や単語がある時、感じの持つもともとの意味から連想するのは正しい方法です。しかしながら、「予す」の場合はそのような連想からでは正しい読み方を導き出すことは難しいでしょう。
実は「予す」は「ゆるす」と読みます。これはなかなか知らないという人も多いのではないでしょうか。
「予す」はどういう時に使う?例文も紹介!
via pixabay.com
「予す」が「ゆるす」と読むことは分かりましたが、今までに使ったことはないという人も多いでしょう。実際「予す」という読み方が気になっている人は、クイズ番組などで見かけたという人も多いのではないでしょうか。
漢字辞典で「予」という漢字を調べると、訓読みとして「あらかじ-め」、「かね-て」、「われ」、「あた-える」、「ゆる-す」のように、実際に「予す」という言葉もあります。ですが、それらは全て【常用外】の使われ方のため、一般的には使われません。そのため「予す」という単語の使い方を調べようと思っても「そもそも一般的ではない」という結論に至るでしょう。
漢字辞典で「予」という漢字を調べると、訓読みとして「あらかじ-め」、「かね-て」、「われ」、「あた-える」、「ゆる-す」のように、実際に「予す」という言葉もあります。ですが、それらは全て【常用外】の使われ方のため、一般的には使われません。そのため「予す」という単語の使い方を調べようと思っても「そもそも一般的ではない」という結論に至るでしょう。
「予す」と「許す」や「赦す」の違いとは?
via pixabay.com
「ゆるす」という言葉を聞くと、「予す」よりも「許す」や「赦す」という漢字を先に想像する人の方が多いでしょう。では、「予す」と「許す・赦す」はどのような違いがあるのでしょうか。
実は結論から言うと、これらの3つには違いがありません。元々は「ゆるす」という意味を持ち、「あらかじめ」とも読む「豫」という漢字が、簡略化されて「予す」という表記をすることになったのです。その上で、漢字の持つ「予定」という意味とそぐわないことから「許す・赦す」という表記が使われることになりました。
そのため「許す」を「予す」と書いても、特に間違いというわけではありません。ただし、これは一般的に使われないため、意味が通じることはめったにないでしょう。さらに「予」には「ゆる-す」という訓読みがあるものの、かなり特殊なため漢字辞典にも載っていないこともあります。そのためテストなどで「予してください」と書くと、減点される恐れもあります。
実は結論から言うと、これらの3つには違いがありません。元々は「ゆるす」という意味を持ち、「あらかじめ」とも読む「豫」という漢字が、簡略化されて「予す」という表記をすることになったのです。その上で、漢字の持つ「予定」という意味とそぐわないことから「許す・赦す」という表記が使われることになりました。
そのため「許す」を「予す」と書いても、特に間違いというわけではありません。ただし、これは一般的に使われないため、意味が通じることはめったにないでしょう。さらに「予」には「ゆる-す」という訓読みがあるものの、かなり特殊なため漢字辞典にも載っていないこともあります。そのためテストなどで「予してください」と書くと、減点される恐れもあります。
「予す」以外にもあるの?簡単なのに読めない熟語を紹介!
via pixabay.com
「予す」のように、一見すると簡単な漢字に見えるのに、意外と読み方が分からないというケースは少なくありません。常用漢字ではないから使われないこともあれば、単語自体があまり一般的ではないから文字で見る機会自体が少ないということもあるでしょう。
では、「予す」の他にはどのような漢字が「読めそうなのに読めない」ということになりがちなのでしょうか。ここでは最後に、簡単なはずなのに読めない人が多い5つの単語を紹介していきます。
では、「予す」の他にはどのような漢字が「読めそうなのに読めない」ということになりがちなのでしょうか。ここでは最後に、簡単なはずなのに読めない人が多い5つの単語を紹介していきます。
強か
via pixabay.com
「強い」や「強敵」という言葉で見ることも多い「強」という漢字ですが、ここにひらがなの「か」がつくと読めない人が多いのではないでしょうか。実はこの「強か」という単語は「したたか」と読みます。
「手ごわい人」を意味して「強かな人だ」ということもあれば、「とても」のような意味で「したたかに頭を打つ」という使い方をすることもあります。また最近では「あの人、実は強かだよね」のように「弱く見せているけど、内心では色々と考えているちょっと腹黒い人」という意味で「強か」という表現を使う人も増えているようです。
「手ごわい人」を意味して「強かな人だ」ということもあれば、「とても」のような意味で「したたかに頭を打つ」という使い方をすることもあります。また最近では「あの人、実は強かだよね」のように「弱く見せているけど、内心では色々と考えているちょっと腹黒い人」という意味で「強か」という表現を使う人も増えているようです。
生憎
via pixabay.com
「生」も「憎」もそれほど難しい漢字ではありません。「生きる」や「生もの」のように「生」という漢字は毎日見るといっても過言ではないほど一般的な漢字ですし、「憎」という漢字に関しても「憎い」という言葉を目にすることも多いでしょう。
その二つを組み合わせた「生憎」は「あいにく」という読み方をします。「予想よりも不都合なことが起きた」という時に使われる単語として広く知られている言葉です。「あいにくの天気」のように頻繁に使う言葉ですが、漢字表記は知らなかったという人も多いのではないでしょうか。
その二つを組み合わせた「生憎」は「あいにく」という読み方をします。「予想よりも不都合なことが起きた」という時に使われる単語として広く知られている言葉です。「あいにくの天気」のように頻繁に使う言葉ですが、漢字表記は知らなかったという人も多いのではないでしょうか。
論う
via pixabay.com
「論より証拠」や「理論」のように「論」という漢字も日常的に見ることが多い漢字です。ですが、それにひらがなの「う」がくっついて「論う」となると、読めなくなる人も多いのではないでしょうか。
「論う」は「あげつらう」と読みます。この単語の場合、今までに紹介したものとは違い、あまり日常的には使わない言葉かもしれません。「論う」は、特に人の欠点や弱点をとやかく言うことを意味する言葉です。「人の嫌なことばかり論って、あの人は嫌な人だね」のように使われます。
「論う」は「あげつらう」と読みます。この単語の場合、今までに紹介したものとは違い、あまり日常的には使わない言葉かもしれません。「論う」は、特に人の欠点や弱点をとやかく言うことを意味する言葉です。「人の嫌なことばかり論って、あの人は嫌な人だね」のように使われます。
奇しくも
via pixabay.com
「奇妙な物語」や「奇怪な動き」のように、ちょっと不気味なものを表現する時に使われるのが、この「奇」という漢字です。この漢字にひらがなの「しくも」が組み合わさることで「奇しくも」という言葉になりますが、こちらも読めない人が多いのではないでしょうか。
これは「くしくも」と読み「偶然にも」や「不思議なことに」という意味を持ちます。「奇しくも誕生日が同じ二人だった」のような使われ方をします。漢字自体は読めなくても「奇」の持つ意味と似ていることから、なんとなく意味は想像できるかもしれません。
これは「くしくも」と読み「偶然にも」や「不思議なことに」という意味を持ちます。「奇しくも誕生日が同じ二人だった」のような使われ方をします。漢字自体は読めなくても「奇」の持つ意味と似ていることから、なんとなく意味は想像できるかもしれません。
確り
via pixabay.com
「確かに」や「確実に」などといった言葉に使われることが多いのが「確」という漢字です。この「確」にひらがなの「り」を組み合わせて「確り」という単語になりますが、これもなかなか読みづらいと感じる人も多いでしょう。「かくり」ではないし、どう読めば良いのか悩む人も多いのではないでしょうか。
実は、これは「しっかり」と読む単語です。「しっかりと覚えておく」や「しっかりとした人物」のように、日常会話で使うことも多い表現でしょう。ただし、特殊な書き方ですので、漢字で書くと意味が伝わらないことも多く、注意が必要です。
実は、これは「しっかり」と読む単語です。「しっかりと覚えておく」や「しっかりとした人物」のように、日常会話で使うことも多い表現でしょう。ただし、特殊な書き方ですので、漢字で書くと意味が伝わらないことも多く、注意が必要です。
1 / 2